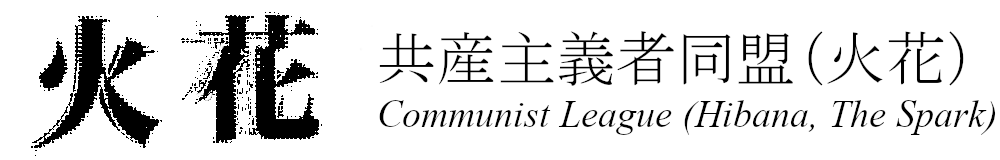状況2025年夏
斎藤 隆雄
473号(2025年09月)所収
一連の日本の選挙が終了して、議会政治の枠組みが決まったが、世界情勢は領土と関税の戦争が吹き荒れており、次の時代の予感が忍び寄る情勢となってきた。そこで、一旦、情勢の整理を行なっておきたい。
1.日本の議会政治:地殻変動は起きたのか?
自民公明の与党の議席が衆参で過半数割れを起こし、喫緊の世論調査によれば、自民党支持が20%となっているようである。これは今世紀に入って最低のレベルを記録したようだ。参院選での比例における政党支持率では、国民民主、参政、立憲の三党が横一線に並んだ(700万票台)。維新が低落傾向にあり、れいわが共産を上回った。これらを見ると、総じて民衆は従来の政治に愛想をつかし、それぞれ注目する野党に投票したということになる。投票率は58.51%で、一億人の有権者の内、約6000万人が投票した。ということは、4000万人は判断を保留している。
さて、マスコミに注目されたのは躍進した参政党なのだが、この間の兵庫県や東京都での地方選挙、あるいは財務省解体デモなどで動員された人々などを見てみても、どうやら従来組織化されていない労働者階級や小資本経営者、自営業者などの中で比較的政治情勢に敏感な層がこの党に流れたようだ。これは従来の自民公明などが張り巡らしていた政治的地下茎が寸断されてきていることを示している。これが一時的なものなのかどうかはもう少し時間が必要だが、面白いことに、石破政権への支持が自民支持層で依然高いという世論調査の結果が出ている。残存した自民支持の20%、あるいは投票を棄権した隠れ自民支持層は比較的冷静に政治を見ていることを示している。
一部のリベラルがこの情勢に危機感を募らせているようだが、総じて見ると日本の有権者はいよいよ自覚した政治的個として成熟しつつあると見たほうがいいだろう。地殻変動という意味では、この流動化した選挙民の多様性こそ、いい意味でも悪い意味でも戦後日本の政党政治における地殻変動ではあるだろう。ただ付け加えるとするなら、近年話題となっているSNS等のマスメディア以外の情報ツールが広がっていることをあれこれと分析しているが、以前としてマスメディアの影響力は強大で、インターネット経由の情報ツールに主導権が移行したという兆候は見られない。むしろ、これらの情報ツールが相互に絡み合ってきたと見るべきだろう。
2.財務省解体デモ:流動化が始まったのか?
注目されたデモは、昨年12月に始まり、今年の2月に千人規模のデモが行われ、各地に広がった。このデモの特徴には二つの側面がある。一つは従来からの官僚攻撃である。日本の政治経済政策は中央官庁が作っており、彼らの利権が反映されたものだというエリート主義批判あるいはディープステート論へと発展する政治的傾向である。もう一つは2019年ごろから話題となっていたMMT理論への依拠である。この理論については既に機関紙でも私は取り上げてきたのでご存知であろうが、この一般的には異端と評価されている経済理論に依拠した政治潮流やデモは、欧州では一昔前にはよく見かけたが、日本でははじめてではないだろうか。しかし、この理論はデフレ下にあった当時の日本には有効であったが、今やインフレが進行している現在においてはほとんど意味をなさない。むしろ有害でさえある。というのは赤字国債が積み上がっている日本でのインフレ状況で、供給潜在能力よりも需要が上まって、円安局面が固定化されている以上、これ以上の債務拡大は歴史的には衰退国家の典型的な道筋をなぞることになるからだ。
さて、もう一方の財務省批判であるが、このデモに参加している人たちはどのような層なのだろうか。
「つまりこのデモに集まっているのは、『もらえるお金を増やす』という発想を持ちにくい人たち、もしくはそうした発想で団結することができない人たちなのではないだろうか。例えば『インボイス廃止』などのコールがしばしば用いられることからも、そこには自営業者やフリーランサーなどの参加者が多いことが窺われる。また、他にも中小企業の従業員や非正規雇用労働者など、労働組合との関わりが薄い人たちが多いと思われる。」(伊藤昌亮『取り残された人々の財政ポピュリズム』世界7月号)
更に、このデモの特徴として指摘しておかなければならないのは、デモ参加者の中に排外主義を煽る人たちがいたことである。つまり、このデモはいわゆる欧米に見られるような積極財政主義の左派的な運動ではなく、どちらかというと、「米よこせ騒動」のような原初的な民衆暴動に近い傾向性が見て取れる。これは新自由主義的な官僚批判を喧伝していた維新のようなものではなく、根底に「我々に金をよこせ」的な福祉要求であり、財務省の緊縮財政主義が生活を直撃する可能性を予見した現在の閉塞状況への怒りであるのだろう。排外主義も「外国人が富を簒奪している」という根拠のない苛立ちに根付いたものだと推察できる。
また、秦正樹氏(大経大教授)の実施した世論調査によれば、これらのデモ参加者の党派的傾向は国民民主、参政、れいわの三党に集中しており、これはSNSなどでの影響を強く受けていることが見られるという(世界9月号)。これは私の推測ではあるが、どうやらこれら諸党へ投票した人々の政治的傾向が財務省デモと重なるとみるなら、従来立憲や共産に投票していた部分の少ない部分がこれらに鞍替えした可能性が考えられないだろうか。
以上、この財務省解体デモに見られる社会的状況は確かにコロナ禍以降の日本の状況が変化してきたことが示されている。
3.トランプの関税戦争
視点を国際政治に目を転じるなら、例の上乗せ関税交渉が25%から15%へ値切られたようである。そもそもこのトランプの全世界を対象とした関税戦争とは何なのかがあまり理解されていない。これはトランプ政権だから始めたと思われているようだが、アメリカの長年の貿易収支と財政収支の赤字は今に始まったわけではないので、いわば定期的に起こるアメリカ帝国政治の痙攣である。いわば第二のプラザ合意のようなものである。おそらく日本は対米関税が25%になったとしても、それは円ドル相場が100円になった時と同じなので、苦境にはなるが崩壊とまではいかないレベルだろう。問題は為替ではなく、関税での調整なので、対米貿易に依存しない経済構造を構築するという選択肢が残されている。トランプの選んだ政策選択は彼が希求する製造業の米本土回帰という目的は実現しそうにもない(そもそも製造業の回帰など現在の国際分業体制下にあって歴史を巻き戻すことが如何に困難か理解できていないし、労働集約型産業で雇用を確保することでさえ、今や機械化/ロボット化が進行しているのだから不可能)。むしろ中国やロシアが進めるグローバルサウス諸国の経済圏の自立を促すだろうから、多元化というよりも二元化が進むだろうというのが一般的な想定。米帝の世界経済に与える影響力が減衰すると同時に、彼らが持っている軍事ネットワークとの齟齬が目立って顕在化することになる。
まだ、対中国との交渉が終わっていないので何とも言えないが、軍事ネットワークの重荷を軽減するためには、戦争は終結させねばならない。ウクライナもガザもトランプにしたら早期決着させたいのだろうが、彼が望むようなものとはならない。ウクライナはソ連崩壊以後の帝国終焉後の再編過程であるし、ガザは更に根深い欧米帝国主義の最後の負債である。イスラエルとロシアの暴走をアメリカ帝国が止められる根拠はどこにもない。
4.我々に求められているものは何か
国内政治の流動化と国際情勢の政治経済両面の行き詰まりが示しているのは、いわゆる資本主義的政治経済の選択肢に多様性がなくなってきたことを示している。日本に限って言うなら、再配分福祉政治も新自由主義的放任政治も、前者は財政状況から不可となり、後者は文化的差異による不適合(注)を起こしているのである。世界情勢が二元化に向かいつつある中で、対米従属構造にある日本は股割き状態であり、外交政治上の岐路に差し掛かっている。
※新自由主義政策は元々普遍的個人主義と社会的協調という前提で成り立っているが、日本の文化風土はそのような個人主義はなく、身内主義があるだけで、欧米的協調精神もないので、この政策は機能しないばかりか、むしろ社会のセーフガードを破壊する機能さえ持っている。
ここで先の選挙でアジェンダとなった減税政策や給付金政策はますます財政状況を解決不可能状態へと追いやるだろうし、対米従属政策の深化を目指している石破政権は軍事的に泥沼に嵌る一方であろう。トランプの関税戦争のおかげで日本の金利はますます上げづらくなってきたので、インフレ進行はこのまま累積することは確定である。つまり、民衆の富の格差は拡大するばかりとなり、閉塞状況もまた累積することとなる。
資本主義経済を前提とした、これからの日本の選択肢は、例えば金利の上昇や対米従属からの撤退、税制改革(累進課税の深化)などによる日本経済復活のシナリオなどは確かに共産主義革命よりは手っ取り早いかもしれないが、そもそもそのような政策が日本労働者階級の解放につながるのかと言えば、ほとんど現状の分断構造は変わるはずもなく、非正規雇用労働者と組織労働者との格差は縮まることはないだろう。もし、資本主義経済をいじる勇気があるのなら、労働政策のもとで資本規制を大胆に実施するしかないのだが、それによって起こることは資本の逃避と労働市場の再編、長期にわたる生産停滞(資本家のサボタージュによる)である。この現象に耐えられる政治勢力があるとは現状では思えない。この程度の政治経済社会上の混乱をあえて招く政策を選択するためには、それ以上に資本主義経済をそのままにしておくよりはマシだと思えるような危機的状況が招来されなければならないだろう。それはおそらく将来的には到来するだろうけれども、その前に展開すべき運動は何なのかを問い直す方がいいのではないだろうか。
国内政治上の問題として取り上げなければならないのは、経済政策ではない。資本主義の世界システム上にある日本経済に関する、資本主義経済を前提とする選択肢はほとんど存在しない。つまり分岐線を引くことができないということだ。国内政治の問題として取り上げなければならない問題は上部構造全体である。法制度と社会文化政策である。資本主義に手を入れる前にこれを解決できていなければおそらくどのような政治制度改革も成功しないだろう。従来から、上部構造の変革は下部構造の変革によって成し遂げられると考えられる傾向にあったが、確かにその側面は否定できないにしても、その下部構造の変革の激烈な震度は強烈な地殻変動がなければ起こり得ない。平時においてなすべき社会運動はむしろこれらの地殻変動を比較的温和なものとなるようにすることの方が革命家にとっての任務なのだ。つまり革命党の社会政策は未来社会の想定される人間の意識構造変革を見通さなければならない。その意味で、今般の選挙で露わになった保守主義や排外主義の政治勢力との戦いをこそ焦点化されなければならないだろう。
ただ問題はこれらの社会意識の変革は単なるスピリチュアルビジネスや自己啓発セミナー的なものとの混同を生み出すことである。社会意識の変容を政治的言語に変換すること、つまり労働者階級の主体性を生み出す協働精神を開示するものでなければならない。これは抽象的な表現としてはできても、具体的な政治課題へと落とし込むことは極めて困難である。そして、それこそが我々に求められていることなのだ。
更に言うなら、これらの政治的言語は往々にしてリベラル左派の課題と表層的には重なり合うように見え、フェミニズムや人権、環境問題など扱い方を間違えれば、常にとんでも理論へと転がり得る危険性を孕んだものでもある。故に、実は安易そうに見えて実に困難な課題であるということも言い添えておきたい。