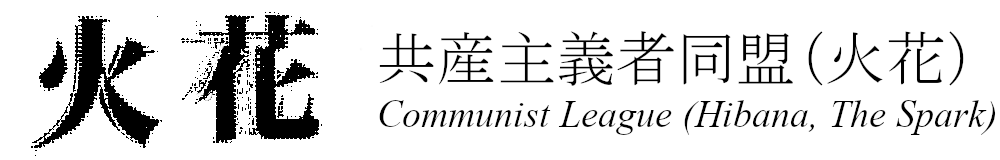途上の人―流広志同志の追悼にかえて
松田 健
471号(2025年06月)所収
こんなに早く流同志に別れを告げることになるとは思わなかった。
それぞれの日常活動の場を異にしてから相当な年月が経ったが、私の中の流同志の姿は、時に大股で、時に足元を探りながら、それでもつねに前方を見据えて歩き続けるそれであった。
彼と初めて出会ったのは、’80年代の初め、京都の東九条松ノ木町40番地「生活と人権を守る会」のプレハブ事務所だった。京都駅にほど近い七条部落の南、東九条には多くの在日韓国・朝鮮人が暮らしている。40番地は、東九条の他の町と堤防で隔てられた鴨川の河川敷にあり、百軒近い住居が密集していた。「不法占拠」「0番地」と呼ばれ、水道もなく、在日の人々が大部分を占める住民たちは生命と健康を脅かされていた。そこには、差別と排除の実態があからさまに示されていた(「市民」たちの多くはそれが見えなかった、いや、見ようとしなかった)。
私たちは、当時、40番地自治会を中心とする水道設置要求の対行政闘争に参加した。住民闘争は、差別行政とその歴史責任を厳しく問うものであった。この闘争は、七条部落や東九条における地域闘争の経験を引き継ぐものであったとともに、それらが40番地を取り残してしまったことへの内在的批判の質を持つものでもあった。
部落民・在日・下層労働者、「三つの主体」の結合を掲げた東九条青年会を先駆けとするこの闘争に、多くの学生運動活動家が合流した。その目的や関わり方はさまざまだったが、それまでの運動経験で獲得してきた「反帝闘争」「階級闘争」の諸概念を東九条での経験を通して深化させたいという志向は共通していたと思う(その意味で、東九条は学生活動家の「学校」でもあった)。流同志も私もそうしたメンバーの一人だった。
私たちは、行動をともにするなかで、よく意見を交わした。中心となったのは、自分たちは何を目的に、どういう責任を負って東九条の運動に参加するのか、という問いをめぐるものだった。2人の問題意識は、端的に言えば、次の点で共通していた。運動の中に共産主義を刻印するために何をするのか? プロレタリアートのヘゲモニーを形成するために、地域共同闘争の具体的課題においてどんな判断と行動をとるべきか……流同志のまなざしは会った当初からここに向けられていた。もちろん、地域運動の現実に新たな要素を加えたり、変容させたりするような「答え」は容易に見出せるものではない。私たちは、まず、階級闘争の中で自身が代表し、責任を負うべき共産主義実践の内容を定め、運動との働きかけの関係を築くことが「答え」の条件だと考えていた。
私が東九条の運動に参加し、流同志と出会ったのは、共産同(火花)始動の時期である。火花は、四分五裂状態の共産主義運動の統合に向けて、まず、プロレタリアート独自の闘争を<綱領・戦術・組織>として明確に措定すること(もとより、批判と修正に開かれたものとして)、わけても、綱領を軸とした論争を提起した。綱領は、資本主義・帝国主義と階級闘争の批判(原則的部分)と、共同で実現すべきプロ独の具体的な構造・政策・制度(実践的部分)から成り立っている。前者をめぐる論争を深化・発展させること、同時に、そのためにも、後者の内容をさまざまな大衆運動の具体的課題と結びつけること。火花はこの経験を組織し、今の運動の中に革命(その担い手)を準備することをめざした。
流同志とはこの目的を共有することになった。
‘80年代半ば、火花は、次の一歩として、さまざまな政治共同行動の場に、私たちの旗を持ち込むことに踏み出した。政治行動部隊の組織化である。
当時、三里塚闘争の分裂が進行する中で、私たちはこの状況を乗り越える方途を探るべきだと訴えた。革命への道筋をめぐる党派の分裂が大衆運動の分裂とつながるという事態、それは、共産主義者の運動への働きかけの条件を狭め、対話と論争や、民主主義の試行・実験の空間を狭めることになると考えたからだ。私たちは、革命を―抽象化・彼岸化された目的としてではなく―直接めざす運動の創造に向けた「論戦と共同行動」を政治行動の場で呼びかけた。
流同志は一連の活動の中で、つねにその先頭にいた。とくに、綱領的内容を中心に、労働運動、大衆運動の課題や党派間の対立・論争の問題点を明らかにすることに力を注いだ。新たな論争をつくりだすために旺盛に書いた。’90年代以降、15年にわたって機関誌「火花」に掲載された論文はその所産である。
流同志は、書くために、よく学んだ。新しい課題と自分の仮説、理論・作業上の見通しを熱心に語る姿が印象に残っている。共産主義者の論争をより活発なものとし、分散した個々をつなぐような営為をつくりだしたいと彼は願っていた。活動のフィールドを変えたのも、このしごとにさらに力を注ぎ、論戦の機会を広げるべきだと思い定めたからだろう。
流同志は途上の人であった。彼自身、共産主義論争史の中に自分の足跡を記したいと語っていた。そして、彼はたしかに足跡を記した。資本主義そのものをどうするのか、が人々の意識や運動の前面に表れ出している今、彼の歩みから新たな道を切りひらいていく可能性を探りたいと思う。